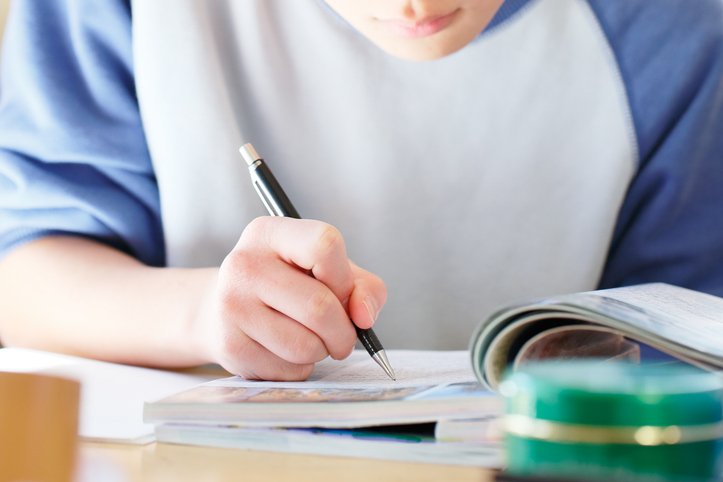2023.08.01
倍率が高い学校はあきらめた方が良いの?受験生になる前に「倍率」について理解しておこう!

志望校を決めるポイントのひとつに「倍率」があります。倍率が高い学校=競争率が高いというイメージから、倍率が高い学校の受験をあきらめていませんか?
実は倍率の高い・低いが単純に合否を決めるわけではありません。倍率を正しく理解し、志望校の選択や受験対策に活かしましょう。
Contents
入試において「倍率」が示すものとは

倍率とは「受験者数÷募集人数」で算出した数を指します。かんたんに言えば「〇人に1人が合格する」の〇人の部分を表したのが、倍率です。
たとえば募集人数100人の学校に対して300人の受験者数がいた場合の倍率は、「300(受験者数)÷100(募集人数)=3」で「3.0倍」=3人に1人が合格することになります。
一方、同じ募集人数100人の学校に対して500人の受験者数がいた場合の倍率は、「500(受験者数)÷100(募集人数)=5」で「5.0倍」=5人に1人が合格することになります。
単純に考えると、倍率が高いほど合格しにくく、低いほど合格しやすいことになります。そのため倍率は学校の入試難易度をはかる指標とされることも多く、「競争率」と呼ばれることもあります。
倍率がその学校の入学難易度を決定するものではありませんが、難易度を決めるためのひとつの要素として考えられます。
志願倍率・受験倍率・実倍率 3種類の違いについて

倍率は「志望倍率」「受験倍率」「実倍率」の3種類があります。3種類の倍率は応募状況、受験状況、合格状況時に発表されます。3種類の倍率の違いと正しい意味をおさえておきましょう。
志願(応募)倍率
志望倍率(応募倍率)とは、募集人数に対して「何人応募があったか」を表した倍率です。「志願者数÷募集人数」で算出され、出願締め切り後の最終応募状況で発表されます。
受験倍率
受験倍率とは、募集人数に対して「実際何人が受験したか」を表した倍率です。「受験人数÷募集人数」で算出され、入試後の受験状況で発表されます。
実倍率
実倍率(実質倍率)とは、受験者数に対して「何人が合格したか」を表した倍率です。「受験者数÷合格者数」で算出され、合格発表後に公表されます。実倍率が学校ごとの最終的な倍率と言えるでしょう。
3つの倍率は、応募、受験、合格発表を経て変動することがあります。たとえば、「応募したもののすでに第一志望に合格している」、「体調不良で欠席した」などの理由で入試当日の受験者数が減れば、志望倍率よりも受験倍率は低くなります。特に私立高校は併願する受験生が多いことから、入学辞退者を見越して多めに合格者を出す傾向にあります。その結果、受験倍率と実倍率に大きな差が出るのです。
応募倍率は高かったものの、発表された最終倍率は予想よりも低かった、ということもあります。
高校の倍率はどこで参照できる?
高校ごとの倍率は各高校の公式ホームページで公開しています。公立高校の倍率は、各都道府県の教育委員会のホームページでも閲覧可能で、一覧になっているため複数の高校の倍率を比較しながら参照することができます。
「高い倍率」って一般的にどれくらい?
受験において、どのくらいからが高い倍率に該当するかは、明確な定義はありません。私立か公立か、受験する地域やコースにもよりますが、高校入試であれば1.5倍以上を「高い倍率」と捉えられることが多くなっています。
ただし、「1.5倍以上の学校は合格しにくいから受験するのはやめよう」と判断するのは間違いです。過去の倍率と比較して「今年は高い・低い」と判断する程度に留めておきましょう。
倍率が高いからといって、あきらめるのはまだ早い!
前述どおり、倍率が高いからという理由で受験する学校の選択肢を狭めてしまうことはおすすめしません。出願後に発表されるのは志願倍率です。最初に学校を志願した人数を募集人数で割ったもののため、最終的な受験者数から算出される受験倍率や実倍率は変動する可能性があるためです。つまり、当初の志願倍率が高いからと言って難易度が高いとは限らない可能性があります。
倍率が高くてもしっかり準備をすれば十分合格が狙えますし、倍率が低くても本番で油断からミスを招いてしまう可能性もあります。
興学社学園グループでは受験生としての意識面を成長させる為に合格出陣式を行っています。生徒の受験生としての意識を高めることができます。また、夏期講習以外にも4日間の夏期特訓会を実施しています。ぜひ興学社学園グループの塾で受験対策をしてみませんか?
反対に「倍率が1倍=全員入れる」ではない
ごくまれに、倍率が1.0未満で表示される学校もあります。これは募集人数に対して志願者数が少ない、いわゆる「定員割れ」をしている状態です。「定員割れ=全員合格できる」と考える人も多いかもしれません。気を付けてほしいのが、定員割れの学校を受験しても、絶対合格するとは限らないことです。
各学校では、入試の合格点数の最低ラインを設定していることがほとんどです。そのため、定員割れの学校を受験しても、入試の点数が最低ラインを上回らなければ合格できません。
たとえ受験する学校が定員割れになったとしても、油断は禁物です。ほかの受験生との競争はなくなりますが、その学校の設定している最低ラインを越えるだけの受験勉強や準備は必要です。定員割れをしている、または極端に倍率が低い学校でも最低ラインが設定されていることを忘れずに、しっかり受験勉強をして対策をしておきましょう。
過去の倍率を参考にするときは、3年分ほど振り返ろう

今年度だけではなく、前年度の倍率を比較し参照する人も多いかもしれません。今年の倍率のほか、前年度をふくめた複数年度の倍率を確認しておくのがおすすめです。高校受験には、前年度倍率が低かった高校や学科は翌年に志願者が集中、逆に前年率倍率が高かった高校や学科は敬遠されてしまい、翌年志願者が減る「揺り戻し」または「隔年現象」が起きる可能性があります。倍率は3年分程度を見て判断するようにしましょう。
また、入試制度に変更があった都道府県や、募集人員の増減があった高校・学科を受験する場合は注意が必要です。変更の影響を受けて、受験者の動きも変わる可能性があります。変更にともなって志望していた学校の人気が高まり倍率が上がってしまうこともあれば、逆に人気がなくなり下がることもあります。
志願倍率が出るのは出願申し込みを締め切った時点のため、受験本番まではまだまだ時間はあります。志願していた学校の倍率が急変しても、慌てずに受験の準備を進めましょう。
重要なのは「倍率の高さ」ではなく、「志望校の合格点を超えられるか」

受験生にとって、倍率は志望校の難易度を考えるときの大切な指標のひとつとなります。そのため「倍率が高い学校はあきらめて、倍率が低めの学校にしておこう」「自分が挑戦しても受かりそうな学校にしておこう」と考える人も多いかもしれません。しかし、受験する学校の指標として重要なのは、倍率の数値だけではありません。
大切なのは、志望校が設定している合格点のラインを越えられるかどうかです。倍率が高くても偏差値の低い受験生の割合が高ければ合格しやすくなります。逆に倍率が低くても、偏差値の高い受験生が多ければ合格する可能性は低くなります。
志望校の倍率のみを見るのではなく、自分の模試の結果や偏差値も志望校選びや受験対策の重要な指標となります。志望校の受験生全体から見て、自分がどの程度のポジションにいるかも確認しておきましょう。
最後に大切なのが、自分がどの学校に行きたいかです。倍率で学校を選ぶのではなく、自分にとって行きたいと思う学校へ合格するためにしっかり準備をしておきましょう。
まとめ
受験における倍率について次のポイントを押さえておきましょう。
・倍率とは、「〇人に1人が合格する」を表した数値。「受験者数÷募集人数」で算出きる
・倍率の高い低いのみで難易度を判断することはおすすめしない
・倍率1.0未満の定員割れの学校でも、受験生全員が合格できるとは限らない
・倍率を参照するときには、「揺り戻し」や「隔年現象」が起きる可能性を踏まえて、前年度を含め過去3年分を振り返ること
・志望校は倍率だけでなく、模試の結果や偏差値、そして「自分が行きたいか」をふまえて決めること
志望校合格を目指すなら興学社学園グループがおすすめ!
興学社学園グループの高校受験コースは、上位・中堅公私立高校の高校受験コース、難関国公私立高校の難関校受験コースを設けています。合格への力強いサポートを実現するために、学習指導だけでなく、生徒とのコミュニケーションを重視し、一人ひとりに寄り添った指導を行っています。
また、学力向上を目指すための保護者会や、学習目標や志望校の決定に向けた生徒面談や保護者面談、三者面談などを通じて、最新の受験情報を提供しています。無料体験授業も随時実施していますのでお気軽にお問い合わせください。
興学社学園グループでは受験対策として、内申対策と偏差値対策の両方を行っています。また、学習だけでなく、進路指導や学習に対するアドバイスも行っています。ぜひ興学社学園グループの塾で受験対策をしてみませんか?